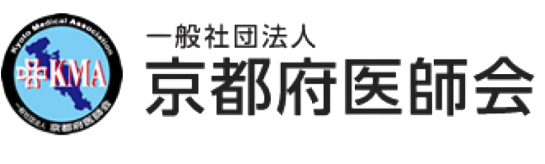京都府医師会について
会長ご挨拶
わが国では、いわゆる「団塊の世代」が75歳を迎え、人口のうち65歳以上の高齢者が占める割合(高齢化率)が約30%に達しました。約3人に一人が高齢者という超高齢社会です。社会の高齢化はこれからも進み2040年には「団塊ジュニア世代」が65~70歳となり、高齢化率がピークに達します。さらに2054年にはわが国の人口は1億人を下回り、全人口に占める75歳以上の割合が25%に達すると推計されています。超々高齢社会です。高齢社会の課題は、社会保障をどのように持続させるかということです。
わが国の社会保障制度は自助、共助、公助の組み合わせで維持されています。自助というのは、自分で助けるということです。医療機関の窓口で支払う自己負担分は自助と言えます。共助というのは、我々国民が負担して作っている保険制度のことです。保険は病気になったときに医療費が高額のため支払えない、経済的理由で医療が受けられないようなことが起こらないように、病気でない人も等しく負担して、いざというときに備える助け合いの仕組みです。共助では対応できない困窮などの状況に対し、受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などを公助として位置付けています。このように社会保障制度は、基本人と人の助け合いで成り立っているのですが、高齢化が進むと病気になる人が増えてくるため、その医療費を保険だけでは賄えなくなるのではないかと心配されています。
一方で、わが国の平均寿命は男性が81.09歳、女性は87.14歳となり、90歳を迎える人の割合は男性で26.0%、女性で50.1%となりました。まさに人生100年時代です。ここで気になるのが、健康寿命です。健康寿命とは健康上の問題で日常生活に制限のない期間のことですが、男性で約9年、女性で約12年も平均寿命と差があります。つまり、人生の最後の約10年間何らかの健康上の制限を持って生活しているということになります。健康寿命が延伸し、医療や介護のお世話にならないで済めば、医療費や介護費用も節約でき、必要な時に、必要な人が保険を使うことができます。
「最後まで元気でいたい。」「自分のことは自分でしたい。」はみんなの願いです。その願い叶えるために「かかりつけ医」がお役に立ちます。「かかりつけ医」とは「健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」のことです。つまり、「かかりつけ医」はいつも皆さんのそばに寄り添い、必要な時に必要な医療に必ず繋げてくれるのです。「かかりつけ医」は、患者さんの自由な意思によって選ばれるべきです。医師会では診療科に拘わらず、「かかりつけ医」の機能を発揮できるように「かかりつけ医機能研修制度」(日本医師会)を活用して、安心・安全な医療が提供できるよう質の向上に努めています。 患者さんから信頼されてこそ、なんでも相談していただける。その信頼にお応えするために私たちは研鑽を重ねています。 皆さんのそばにいる、信頼できる「かかりつけ医」を見つけてください。
令和7年6月15日

一般社団法人 京都府医師会会長 松井道宣